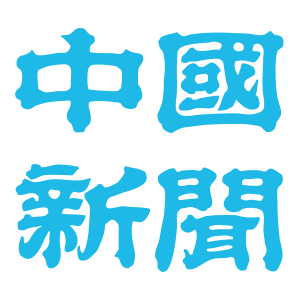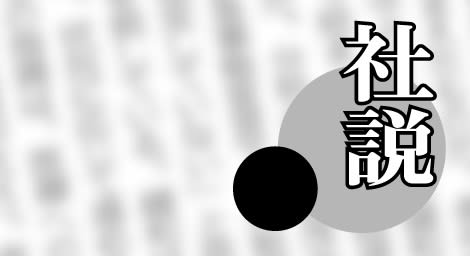
西日本豪雨の発生から、きょうで6年を迎える。中国地方では災害関連死を含めて、251人が命を落とした。
この夏も日本列島は大雨に見舞われている。自分が暮らす場所のリスクを把握し、いざというときにどう行動するかが問われ続けていよう。
一方で、あの日の教訓の風化が忍び寄ってはいないか。県立広島大大学院の研究者による毎年の意識調査が象徴的だ。広島、岡山、愛媛3県の1万人近くの回答からは自分の地区の避難場所を知っているかや、もし指示が出たら避難するかなどに関し、明らかな意識低下を感じ取れる。
そうした中で、広島県内では自治体主催の追悼式がことしは営まれない。5年を一つの節目としたのだろう。語り継ぎ、教訓として伝える地域と住民の役割は重くなる。
足元の災害史も見つめ直したい。広島県坂町の自然災害伝承公園にはあの日、転がり落ちた巨石をモニュメントとした坂町水害碑が建立されている。6年前の死者のうち17人の名前とそれ以前の4回の水害の記録を刻む。すぐ近くに、この地で46人が亡くなった1907年の豪雨の碑もある。「自分の命は自分で守る」。公園の表示板の言葉は住民ならずとも重い。
水害は繰り返す。終戦直後の枕崎台風を分析すれば、土石流で死者が出た場所の9割近くが現在の土砂災害警戒区域と重なるという。過去の教訓が薄らいだところに災害が襲い、また死者が…。そんな連鎖は断ち切りたい。さらに言えば災害の記録がなくても近年の開発に伴い、リスクを背負う場所もあろう。異常気象が今後も続けば、いつ何が起きてもおかしくない。
自治体も住民任せにせず、地域の継承活動に積極的に関与すべきだ。学校の防災教育のカリキュラムが大きな意味を持つのは言うまでもない。子どもたちは入れ替わり、教員は異動していく。だが命を守る営みに終わりはない。
西日本豪雨の被災地を見渡せば、現実問題として取り組みに温度差がある。小田川の決壊で甚大な浸水被害が出た倉敷市真備町には住民の交流拠点となる市の広大な復興防災公園が今週、開園した。それに比べると広島県内は被災地が分散するため、全体像を伝えにくいきらいがある。
来月には広島土砂災害から10年となる。その被災地に開館した広島市安佐南区の「豪雨災害伝承館」ともさらに連携したい。あちこちの被災地をネットワーク化し、かつデジタル技術も駆使して、災害を知らない世代が過去にさかのぼり、何が起きたか追体験できる。そんな工夫は今からでも可能ではなかろうか。